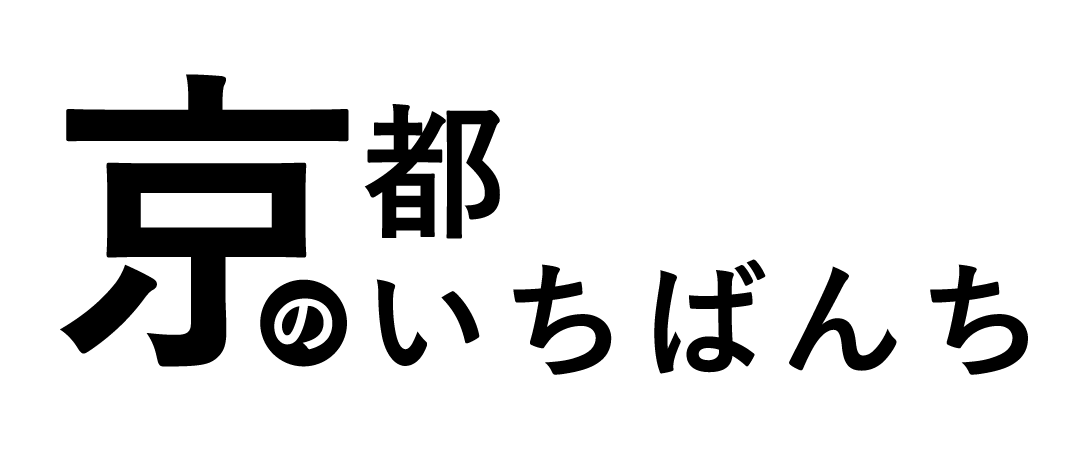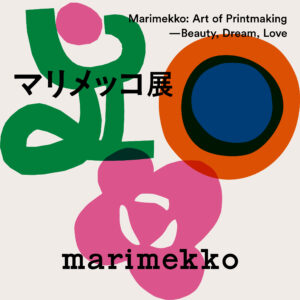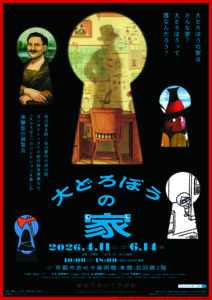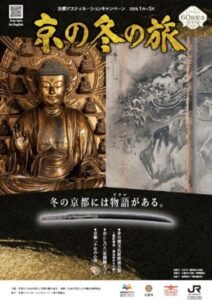京都100本菖蒲、いざ開幕!
5月5日・端午の節句の朝10時。松原通沿いの「大西常商店」前には、すでに多くの人が集まっていました。
本日開催の「京都100本菖蒲」に参加する方々、そして見学に駆けつけた方々です。
この日は、京扇子の老舗「大西常商店」の女将・大西里枝さんが京都市内5カ所を巡り、菖蒲打ちに挑戦。合計100本の菖蒲を叩き尽くす“100本勝負”が行われました。
「京都100本菖蒲」のイベント概要や「菖蒲打ちってなに?」については、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

京都100本菖蒲、開催の様子
女将、全力の菖蒲打ち!

まずは初回。店内から姿を現した大西さんが、参加者や見学者の期待を一身に集めます。
「いきます!」の掛け声とともに始まったデモンストレーションでは、10秒間、全力で菖蒲を地面に叩きつけ。
顔を赤らめ、全身を使ったその打ち込みは迫力満点。
迫力のあまり、思わず息を呑む参加者たち。スマホを構えて動画や写真を撮る姿も多く見られました。
かつては子供の遊びだった菖蒲打ち。けれど、この日の菖蒲打ちはまるで“大人の本気の勝負”。
地面に叩きつける音と大西さんの真剣な表情が、ただの遊びとは思えないほどの凄みを放ちます。

ちなみに今回は、「より大きな音が出る方が勝ち」「ちぎれたら負け」という本来のルールではなく、“ぐちゃぐちゃに叩きつける”ことを楽しむスタイルでの開催。迫力と爽快感をとことん味わう場になっていました。
参加者も本気モード

その後は参加者も体験。
まずは大西さんの全力デモンストレーションで勢いをつけたあと、「もっと腰を落として!」「10秒ね!」と大西さんが檄を飛ばし、参加者全員が一斉に菖蒲打ちをスタート!
地面を叩く音が何度も響き渡り、会場全体が勝負の空気に包まれました。

中には、子供たちによる参加も。
大人顔負けの力強さで菖蒲を叩きつける様子に、打ち終えると自然と拍手が沸き起こっていました。
菖蒲打ちを終えた後の参加者の表情は皆さん晴れやか。
ある参加者は「叩きつけることで気持ちもスッとしました!」と笑顔を見せていました。

最後は、大西さんから参加者一人ひとりに「いけずコースター」が手渡されます。
しっかり“いけず文化”も継承──そんな締めくくりとなりました。
女将は自転車で巡業!

今回の京都100本菖蒲、驚くべきはその移動手段。
なんと大西さんは、菖蒲を前かごと後ろの荷台に満載し、自転車で京都市内5カ所を巡業していたのです!
10時の初回を終えると、大西さんは自転車にまたがり、颯爽と次の会場へ。
「次の“勝負”の時を待つ菖蒲たち」が前後に積まれた自転車は、街中でもひときわ目を引く存在でした。

参加者たちが熱気を残して見送る中、大西さんは風を切って出発。
「えっ、自転車で巡るの!?」──そんな驚きの声が上がる中、菖蒲を積んだ自転車が街を駆け抜けていきました。
鳴海餅本店でのクライマックス

15時の最終回は、上京区の鳴海餅本店が会場。最終回とあって、参加者や見学者の熱気もひときわ高まっていました。

開始前には、会場を快く提供してくれた鳴海餅本店の鳴海力哉さんが登場。大西さんに、グリーンティーと端午の節句ならではの柏餅を差し入れ。最後の一踏ん張り前にしっかりエネルギーチャージです。

さらにこの回では、参加者全員に鳴海餅本店特製のお赤飯が特別に配られるという嬉しいサプライズも。
大西さんと鳴海さんは、実は幼稚園時代からのご縁があるそうで、今回の企画にもいち早く賛同し、場所を提供してくれたとのこと。
伝統行事を支えるこうした地域のつながりも、とても印象的でした。

最後の一打が終わると、自然と参加者とスタッフ全員から拍手が沸き起こり、達成感と一体感に包まれた幕引きとなりました。

打った後の後始末までが「京都100本菖蒲」。菖蒲でいっぱいになった道路は、最後にスタッフの皆さんできれいに掃除して、本当のフィニッシュです。
(筆者も、幸運にも余った菖蒲を手に体験した話)
たかが10秒…と思いきや、これが意外と長い! 叩くうちに自然と無心に。
大西さん曰く「一番嫌なやつを思い浮かべると、よりスッキリする(笑)」とのこと。思いっきり打ちつけることで、心も体も浄化されるような爽快感がありました!
京都の街中で繰り広げられた“100本勝負”。女将の全力と参加者の熱意が重なり合った、忘れがたい一日でした。
「京都100本菖蒲」企画の狙いとやってみた感想を聞きました
今回の「京都100本菖蒲」を企画した、ない株式会社岡シャニカマさん、そして実際に巡業を行った女将・大西里枝さんに、企画背景や当日の感想、今後の展望などについてお話を伺いました。
── まずは、今回の企画立ち上げ背景について教えてください。
岡さん:「もともと大西さんは、端午の節句に『菖蒲打ち』という文化を継承するために、(2017年から)店舗前でイベントを開催してはったんです。その様子がSNSでも話題になって、人気になってるし、菖蒲打ちの名前も知られてきた。
ただ、菖蒲打ちは本来、軒先で行うことでその場所の厄を払う意味があるもの。それが毎回、大西常商店の前だけでやるのはちょっともったいないなと感じたんですよね。
だったら、大西さん自身が各所に出向いて菖蒲打ちをするのはどうだろう? という発想が生まれて、“ウーバーイーツみたいに京都中を巡るイメージ”で企画が進んでいきました。」

── 巡業型のイベントにすると聞いて、どう思いましたか?
大西さん:「なんか、いいやんって思いました(笑)。でも、こんなん受け入れてくれる人いるんかな?と思ったら、一番最初に、鳴海さんが『いいよ!』ってすぐに手を挙げてくれて。」
幼稚園が一緒だったというご縁から生まれた、地元らしい素敵なつながりが、今回の実現にひと役買っていたようです。
── 実際にやってみて、参加者の反応はいかがでしたか?
大西さん:「よかったですね! でも正直、こんなにギャラリーが来るとは思ってなくて(笑)。(参加者の)20人だけでやるものだと思ってたんですけど、ギャラリーとして見物の方が想定よりたくさん来てくれました。」
── 例年に比べてギャラリーの方は多かった?
大西さん:「例年より全然多かった!すごい怖かったもん(笑)。特に朝の初回が一番多くて、実は襦袢(じゅばん)姿で実家に着物取りに行ったら、もうすでに人が集まっていて『やばいやばい!』と思って隠れたんですけど(笑)。(開催時間の)30分以上前から来てる方もいらっしゃって、期待して喜んでもらえたようでよかったです。」
── このイベントを通して、参加者にどんなことを伝えたかったですか?
大西さん:「菖蒲打ちって、本当に昔からある風習なんですが、今はだんだん廃れてきてしまっていて。この“ハレの日をお祝いする文化”を、参加しやすい形で体験できるのがこのイベントなので、廃れかけている文化をちょっとでも思い返してもらえたらいいなと思っています。
正直、自分も含めて、今は『この季節にはこれが旬』みたいな感覚がほとんどなくなっていますよね。ビニールハウスがあれば、果物も一年中食べられたりするし、季節感がなくなってきているなと。
だからこそ、今回の菖蒲打ちみたいなキャッチーなものに、『おもしろそうやから行ってみようか』という気軽なところから、“菖蒲といえば端午の節句、5月”っていうのを知るきっかけになればいいなと思っています。そういう意味で、ちょっとした教育的な要素もあるんじゃないかなと感じています。」
── 今後の展望について教えてください。
岡さん:「今回、そもそもギャラリーがめっちゃ多かった時点で、“需要があるな”と実感しました。チケットも、ありがたいことに100個すべて、販売期間内に満席に。来年はもうちょっと規模を大きくするのか、あるいは菖蒲打ち自体が少しずつ広まってきたので、エンタメ要素を入れるのもアリかなとか。何かしら変化を加えて、また新しい形でやりたいなと……まあ、大西さん次第なんですけどね(笑)。」
(間髪入れずに)
大西さん:「やりますよ、これは!」

菖蒲打ちという昔ながらの風習を、現代の京都の街中でここまでダイナミックに再現する。その舞台裏には、文化を絶やさず次世代につなごうとする熱意と、街を巻き込むユニークな発想がありました。来年以降の展開もますます楽しみです!
まとめ:未来へつなぐ、京都の“伝統と遊び心”
伝統文化を絶やさないこと。昔から当たり前に続いてきた行事を、次の世代にも自然に受け継いでいくこと──。
そしてそのために、時代に合わせてユニークな形で発信し続けること。
今回もまた、大西女将の“京都カルチャーの発信屋”としての力を存分に感じる一日となりました。
今後のさらなる活躍にも注目です!